子どものすきな神さま
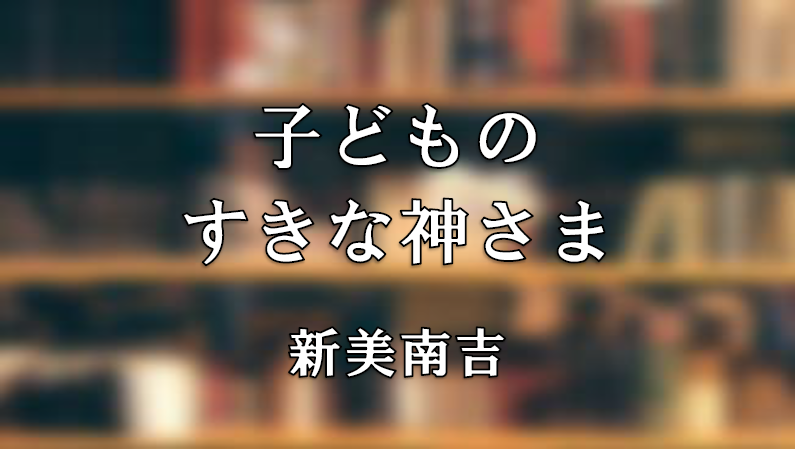
子どものすきな小さい神さまがありました。いつもは森の中で、歌をうたったり笛をふいたりして、小鳥やけものと遊んでいましたが、ときどき人のすんでいる村へ出てきて、すきな子どもたちと遊ぶのでした。
けれどこの神さまは、いちどもすがたをみせたことがないので、子どもたちにはちっともわかりませんでした。
雪がどっさりふったつぎの朝、子どもたちはまっしろな野っぱらで遊んでいました。するとひとりの子どもが
「雪の上に顔をうつそうよ。」
といいました。
そこで十三人の子どもたちは、腰をかがめてまるい顔をまっしろな雪におしあてました。そうすると、子どもたちのまるい顔は、一列にならんで雪の上にうつったのでした。 「一、二、三、四、…… 」
とひとりの子どもが顔のあとをかぞえてみました。
どうしたことでしょう。十四ありました。子どもは十三人しかいないのに、顔のあとが十四あるわけがありません。
きっと、いつものみえない神さまが、子どもたちのそばにきているのです。そして神さまも、子どもたちといっしょに顔を雪の上にうつしたのにちがいありません。
いたずらずきの子どもたちは、顔をみあわせながら、目と目で、神さまをつかまえようよ、とそうだんしました。
「兵隊ごっこしよう。」
「しようよ、しようよ。」
そうして、いちばんつよい子が大将になり、あとの十二人が兵隊になって、一列にならびました。
「きをつけッ。ばんごうッ。」
と大将がごうれいをかけました。
「一ッ。」
「二ッ。」
「三ッ。」
「四ッ。」
「五ッ。」
「六ッ。」
「七ッ。」
「八ッ。」
「九ッ。」
「十ッ。」
「十一ッ。」
「十二ッ。」
と十二人の兵隊がばんごうをいってしまいました。そのとき、だれのすがたもみえないのに、十二番目の子どものつぎで、
「十三ッ。」
といったものがありました。玉をころがすようなよい声でした。
その声をきくと子どもたちは、
「それ、そこだッ。神さまをつかまえろッ。」
といって、十二番目の子どものよこをとりまきました。
神さまはめんくらいました。いたずらな子どものことだから、つかまったらどんなめにあうかしれません。
ひとりのせいたかのっぽの子どものまたの下をくぐって、神さまは森へにげかえりました。けれど、あまりあわてたので靴をかたほう落としてきてしまいました。
子どもたちは雪の上から、まだあたたかい小さな赤い靴をひろいました。
「神さまはこんな小さな靴をはいてたんだね。」
といってみんなで笑いました。
そのことがあってから、神さまはもうめったに森から出てこなくなりました。それでもやはり子どもがすきなものだから、子どもたちが森へ遊びにゆくと、森のおくから、
「おオい、おオい。」
とよびかけたりします。
「神様」が忘れていった、「小さな赤い靴」はこの後どうなったのだろう?ちょっと気になると共に、それでも「子ども」たちと “仲良く” なりたい「神様」の、“承認欲求” (?) が「人間 / にんげん」臭くて微笑ましい。